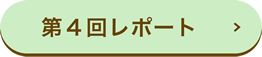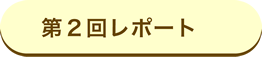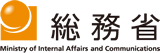


2020年2月2日、全国から地域おこし協力隊員や自治体職員、一般の方も含めて総勢、約1,000名が集結して「第6回地域おこし協力隊全国サミット」が行われた。 その様子の一部始終についてレポートしたい。
オープニングムービーでは高知県四万十町、新潟県十日町市、各地で活躍している、地域おこし協力隊員の様子が流れた。

開会の挨拶では、高市早苗総務大臣が壇上に立った。
2009年、わずか89名でスタートした地域おこし協力隊は、2019年度には約5,500人・全国約1,000の自治体にまで拡大した、国として自慢のプロジェクトとなったことを紹介。
さらに3年間の任期終了後、約6割の隊員が同じ地域に定住し、任期終了後に起業される方の数も2年前と比べ2倍以上に増えるなど、大きな成果を生み出しているという。
総務省では2024年度までに、協力隊員数を8,000人に増やす目標を掲げており、そのために「起業や事業承継の支援強化」「隊員になる方の裾野を広げる」「OB・OGネットワークを強固」にし、PRにも努めたいという。
最後に高市大臣からは「今後インターネットネイティブ世代が、それぞれの地域で開発した産品をネットを活用して全国に展開したり、地域のご高齢の方にネットの使い方を教えたり、テレワークの拠点を地方でも展開してもらえることを希望している。また今回のサミットを通じて、隊員同士がネットワークを広げ、地域おこし協力隊の活躍を全国に発信する機会になることを期待している」というメッセージで締められた。
続いて基調講演に登壇したのは、アートディレクターの北川フラム氏。

「瀬戸内国際芸術祭」「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」などの総合ディレクターを務め、「アートを通じた地域づくり」における第一人者として幅広く活躍されている。
今回の講演で掲げたテーマは、まさにその「アートによる地域づくりの実践」であり、同氏がこれまで手掛けてきた数々の実績を振り返りながら、芸術祭を行う目的やその効果について紹介された。
大地の芸術祭が実施されている新潟県・越後妻有地域は、過疎高齢化の進む典型的な中山間地域。人が都会に流れ、地域コミュニティも衰退していく中で、地域の先行きに不安を抱いている地元に対して、「アート」を通じて何かできないか? それがきっかけで生まれたのが「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」だ。新潟県は北川氏の出身地でもある。

また同じく、同氏が手掛ける「瀬戸内国際芸術祭」が開催される瀬戸内エリアも「過疎高齢化」「地元産業の衰退」など同様の問題を抱えていた。
そうした様々な問題を解決する媒介として「アート」には大きな役割があるという。

北川「地域で作品をつくることによって、この場所がどんな場所か、あるいはこの作品の後ろに広がる風景はどんなものかをアーティストたちは考えます。地域で作品をつくるには地域の方の協力が不可欠。その対話の過程で、地域の人たちは他者(アーティスト)に出会い、地域の魅力を発見することができます。地域づくりには色々な指標があるけれど、僕はやっぱりそこに生きているということに誇りを持つことだと思っています。アート化することで、地域の内外に地域の宝を見せるのです。」
越後妻有では、スクラップ&ビルドをやめ、あるものをできるだけ残し、地域に流れた時間や生活を大切にしているという。また、地元のご高齢の方々も特技を活かして関われるようにすることで、地域・世代を超えた協働が生まれている。
北川「大地の芸術祭の立ち上げ当時は、世界を見渡しても、地域おこしのためにアートが活用されている例は見受けられませんでした。そのため、アートを通じて地域を活性化させるということに懐疑的な方もいらっしゃいました。しかし、地域の住民を巻き込み、彼らが得意としていることを振るえる場とすることで、地域の方が参加することを楽しみにする祭りになってきました。アーティストは地域の人たちが営んできた生活の中に、普遍的な価値を発見します。そのアーティストと地域の方のやり取りの過程が、住民の積極的な関わりへとつながるのです。」
北川「初めは田んぼにポールを立てることに難色を示した住民が、ポールを立てることに同意するだけでなく、ついには「この土地では風がよく変わる。旗をつけたらいい」と提案するまでになってくるのです。
そして、その光景を見ながら家族に「じいちゃんが小さい頃、この瀬でハヤを獲っていた」と地域の歴史をうれしそうに話す、それはすばらしいことだと思います。」


20世紀以降の社会は、均質空間の考えが台頭し、インターネットの発達による情報の均一化によって、「世界の記号化」が急速に進んできた。その結果、世界の大都市は同じような景色となり、便利で快適である一方、固有の文化や生活は失われることとなった。そのような都市に対して多くの人が疑問を持ち、地域に注目し始めているという。
北川「芸術祭は現代美術のファンが担っているわけではありません。地域の文化が捨てられていくということに対して、多くの人たちが動き出しており、それは国内にとどまらずアジアや外国の方の積極的な関わりにより支えられています。人と違ってほめられるのがアート。地域も文化も異なる人たちが関わるには最適です。」

現在、大地の芸術祭は50日間で約50万人の来場者があり、瀬戸内国際芸術祭は100日間で約117万人もの来場者を集めるイベントへと成長。瀬戸内国際芸術祭に至っては、来場者の25%程度が外国人であり、祭りを支える8,000人のボランティアのうちの半数である4,000人が外国人だ。また「地元の小中高校の新設」「社会的な人口増」「インバウンド客の増加」など、開催効果による地域の活性化も見てとることができる。
昨年の12月、第4回「国連世界観光機関(UNWTO)/ユネスコ 観光と文化をテーマとした国際会議」において、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて、「文化の継承」「地域コミュニティ」「人材育成」などに焦点を当てた議論が交わされたのは記憶に新しい。 また著名なアーティストが積極的に地域と関わり作品を発表するなど、地域とアートとの間で多様な展開が生まれている。
最後に北川氏から地域おこし協力隊員等の来場者に向けて「足はしっかりと大地に、目ははるか遠くに、突破口を開いてください」と、これからの活動に対して大きなエールが送られた。

サミット後半の冒頭あいさつでは、元総務大臣で地域おこし協力隊の創設時から現在まで深く関わり続けている、新藤義孝衆議院議員から、これまでの地域おこし協力隊活動の成果の振り返りや、今後「電子化」「キャッシュレス化」に伴う流通基盤の変化による、新たな地域おこしの可能性について熱く語っていただいた。

続いて開催された、有識者によるパネルディスカッション。
テーマは「地域おこし協力隊を誰が、どうサポートする?」で、パネリストには実際に地域おこし協力隊の活動をサポートしている自治体職員、地域おこし協力隊OB、NPO法人スタッフ、地域おこし協力隊サポートデスク専門相談員の4名が参加し、それぞれの立場から、地域おこし協力隊の支援体制における問題点や、課題を解決する具体的な方法論などについて発表した。
コーディネーターは弘前大学大学院 地域社会研究科准教授の平井太郎氏が務めた。

冒頭に平井氏からは「地域おこし協力隊員を誰がどうサポートするのか。これが今、皆さんの最大の関心ごとではないでしょうか? ちなみに『今、私にはサポート体制がしっかりある』という方は挙手してください」との問いかけに対して、手を挙げた参加者はまばら。
地域おこし協力隊の活動の成功には、周囲の関わりが欠かせない。このテーマは、今後の活動を進めていく上で取り組んでいかなければならないことが重要であることが明らかになった。
まずは今回のディスカッションに参加した4名の方より、普段の活動でどのようなサポートをされているのか紹介された。

青森県弘前市の職員である肥後義和氏からは、地元・弘前市が2015年度から地域おこし協力隊員の受け入れを開始し、現在17名の隊員が在籍していること。活動に取り組む中で隊員のサポート体制の必要性を実感し、「地域おこし協力隊活動応援協議会」という組織を立ち上げ、隊員の募集・選考~着任後の支援・アドバイスを行っているという。
こうした活動を通じてサポート体制に必要な3つのポイントとして、以下を挙げていただいた。
- 職員や隊員との信頼関係の構築(活動に関わってこない職員に何か言われても響かない)
- 重層的な相談先の確保(性格が合わない人は必ずいるので、相談しやすい人がいることは重要)
- 多種多様な人的ネットワークへの仲介(人的ネットワークがつながれば自然と活動は広がる)
また最近では「ローカルベンチャー育成」を担う中間組織を設置し、隊員の起業マネジメントや広報活動の支援なども実施しているそうだ。
福岡県上毛町地域おこし協力隊員OBの西塔大海氏は任期終了後、その赴任地でフリーランスとして起業、全国の地域おこし協力隊に対して、様々な活動支援を行っているという。
これまで5年間で80回の研修・講演を開催したり、約500件の相談を受けたりしているが、メインは20の自治体と年間契約を結び行っている支援業務。
同氏が注力しているのは以下の3つ。

- 隊員の募集支援:企画~戦略~募集~採用に至るまでの、効果的な企画・手法の支援
- 隊員の活動・定住支援:集合研修×定期面談×場づくりを通じた隊員&担当職員への支援
- 制度設計支援:様々な困りごとを仕組みで支援するためのガイドライン・マニュアル・会議等の設置
特に隊員と職員、あるいは地域のキーマンとの信頼構築にフォーカスして実施。背景の違う人々が同じ方向を向くためには、お互いの「当たり前」をいかに共有できるかがキーとなる。また、活動支援には隊員たちが地域の中で活躍していける枠組みを準備し、5年後・10年後も、地域のことに一緒に取り組んでいける仲間をどう育てていくかという視点が重要であるという。
さらに隊員たちがどこに住んでいても新たな知識を得られるようにしたいという思いから、オンラインで地域支援活動の様々なノウハウを学べる「さとのば大学」の運営を通じた、地域コーディネーターの育成などにも注力している。

NPO法人ETIC.に所属している瀬沼希望氏からは、これまで同法人が「日本に挑戦者を増やそう!」というコンセプトの元、20年間で約7,600名の若者たちと中小企業をつないできた取組について説明があった。
具体的には、経営者が挑戦したいけれど手をつけられない新しいプロジェクトを、一定期間、若者と試せるチャンスをインターンシップという形で提供するというもの。
新規事業の仮説検証や新商品のアイデア創出のためのマーケティングなどを実施したい企業と、興味関心を深めたい学生をマッチングさせるために行っている同社の取組が、地域おこし協力隊の支援でも活かせるという。
ポイントは以下の3点。
- 受入企業が受入の意図や仮説を明確にする(どの分野でどんな風に活躍してもらいたいかが明確でないとうまくいかない)
- 受入企業・参加者間の目的意識を共有する(ミスマッチが起こるとお互いが不幸になるので、受入前の目的意識のすり合わせは重要)
- 定期的な軌道修正の実施(両者の目的はずれていないか? ゴールに近づいているか? を定期的に確認できる仕組みを作り実施する)
また同法人では、地域の課題解決に挑む多様な当事者と若者をつなぎあわせるための「チャレンジ・コミュニティ・プロジェクト」にも10年以上取り組んでおり、定期的な学びの場づくりに力を入れている。
元地域おこし協力隊員で、現在は地域おこし協力隊サポートデスク専門相談員である野口拓郎氏は、特に青森県内を中心に全国の自治体・隊員への支援活動を行っている。
地域おこし協力隊サポートデスクには2つの窓口がある。
- 一般行政相談員:主に自治体職員からの問い合わせに対応
- 専門相談員:地域おこし協力隊OB・OGを中心に自らの知見等をもとに、現役隊員からの相談に対応

野口氏は専門相談員として「隊員希望者への対応」「行政・地域との関係構築」「地元大学との連携」「地域間比較によるアドバイス」「移住促進」などを行っている。
相談内容によっては、よりふさわしい相談員、知見を持っている相談員を紹介する場合もある。
特に多い相談案件は、以下である。
- 自治体からは事例紹介依頼が非常に多く、募集要件やノウハウ、外国人採用、産休・育休に関してなど
- 隊員からは活動費や自治体・地域との人間関係、公用車の利用や確定申告についてなど
- 協力隊希望者は、協力隊の制度概要、希望する県の事情や地域要件など
サポートデスクの活動によって、以下の効果も表れてきているという。
- 相談データを基にした研究で、よりよい制度運用に関する情報を各種研修で提供できるようになった
- 身近な相談相手として隊員の心理的ストレス解消や、対話を通じた情報整理の支援で、トラブルを未然に防ぐ
- 総務省などの中央機関に現場の声を届けやすくなった
今後、専門相談員のいない、北海道、四国、近畿にいかに情報を届けるか、情報を収集するかが課題。
各パネリストからサポートの取組が紹介された後、それぞれの見解が語られた。

平井「協力隊をうまく機能させるためには、受入側の『ビジョニング』が大事になります。いいビジョンとはみんなが共有できて、それに基づいてみんながやっていることを語れること。協力隊の制度ありきではなく、自分たちにとって本当に大事なことを一つ一つ、確実に掘り起こしていくことで地域の方全員が、共通のビジョンや考えを語れることが理想です。」

西塔「目標や目的を作らされ過ぎていて、そのことについてわざわざ議論したくないことも多いというのが現状。そこで聞き役となれる『第三者』が重要な役割を担うことになる。しっかり話を聞いてくれて事情も分かってくれる人を連れて来れるかどうかが、いいビジョンができる分かれ目だと思います。最初の問いかけの仕方が重要。」
平井「隊員たちが活動を始めてからは、どのように支援を行っていますか?」
西塔「情報のインプットとチームを作っていくプロセスは集合研修で、個人の悩みに寄り添いながらの成長支援は1on1でやるという形です。最初の3か月がすごく大事だと思っています。」
瀬沼「この3か月で転んでしまうと、その後立ち直れないケースが多いですね。」
西塔「最初の3か月で隊員は地域の在り方や自治体の在り方を見定めていて、そこでダメだなと思ったらしばらく起き上がってこない。そうなると、受け入れた自治体職員もこの隊員はやる気がないなと思ってしまい、負のスパイラルに陥ってしまう。自治体職員は隊員に寄り添って、週1回・30分でもいいから話すこと、最初の3か月は毎日顔を合わせて話すということをやっていただきたいなと思います。」
肥後「直接会うことはとても重要。私の場合はあえて仕事の話はせず、自分のプライベートなことを話しますね。自分の話をしないと相手は心を開いてくれないので。」
平井「まずは人間関係を築くことが大切ですよね。現在、支援体制がないという方の場合、自分から応援団を作り出すということもありうると思いますがいかがでしょうか。」

野口「私が隊員の頃はそのような支援制度もなかったので、自発的にネットワークをつくって、お互いに助け合っていました。今後のキャリアで中間支援を目指す人にとっては、逆にチャンスだと思います。サポートの側に立つ場合は、自分の経験を押し付けない、自分の見てきた世界だけで一般論として語らない、そういうところへの目配りが大事です。」
平井「3か月を経て既にこじれてしまっていることもあると思います。その場合、そこからどうやって立て直していきますか?」

野口「そういう時こそどうやって関係を構築しようかと冷静に向き合ってほしいですね。相談先としてサポートデスクや西塔さんのような方を頼ってほしいです。正面衝突してお互いが感情的になってしまうと大変ですから。」
西塔「隊員が地域に入ってすぐは、試用期間のように捉えられている地域の方も多いです。ある隊員から「商品開発で入ったのに2か月以上、レジ打ちしかやらせてもらえず、もう辞めたい」という相談を受けました。受入側に話を聞くと、客層や売れ筋商品、一緒に働いているスタッフの方たちを知った上で、商品開発をしてもらいたいという、すごくもっともな話でした。でもそれが隊員に伝わっていない。これはすごくよくある話。ここで「うまく伝えられない受入側が悪い」と締め出してしまうと地域では働いていけなくて、隊員側の歩み寄りも重要です。「試されているのかな、一度やってみるか」というところから、最初の信頼関係が生まれます。」
瀬沼「学生のインターンシップでも全く同じことが起こっています。伝え方には練習が必要です。また、相手の期待値が100だとしたら、20%くらいその期待を超える要素、ちょっとしたことでいいのでそれを心掛けることが、信頼関係を築いていくことにつながります。」


最後に平井氏から「協力隊の活動は決して一人でやるものではありません。隊員にとっては、自分をサポートしてくれる人を作っていくこともとても重要です。今回の議論をきっかけに、ぜひ自分の仲間を増やしてほしいと思います。」とのメッセージが来場者に投げかけられた。

パネルディスカッション終了後、総務大臣政務官の斎藤洋明氏が会場に駆けつけ、労いの言葉と共に今後の地域おこし協力隊の活動に対して、力強いエールを送った。


今回のサミットでは北は北海道・石狩市から南は沖縄県・北中城村まで、全国39市町村(複数市町村の合同出展を含む)の地域おこし協力隊が、地元の特産品や活動報告を行う展示ブースを出展。
さらに今年はイベント会場に移住情報雑誌「TURNS」プロデューサーの堀口正裕氏がコーディネートする「つながる!おしゃべりラウンジ」を設け、参加者同士の交流促進が図られた。
高市総務大臣や斎藤総務大臣政務官、新藤元総務大臣も展示ブースを視察する中、全国各地の隊員や自治体関係者が交流を図り、会場は大いに盛り上がった。









第6回を迎えた今回のサミットもこれまで同様、隊員や自治体関係者を中心に数多くの方々が参加。 イベントの最後に開催された交流会では、最初に総務省大臣官房地域力創造審議官の境勉から乾杯の挨拶があった後、会場のいたるところで会話が盛り上がっている様子が見受けられた。
今回の感想を聞いてみると、多くの人との出会い、そして全国各地の事例を共有できたことによって「今回の交流をきっかけに、特に横との連携・つながりをもっと強化したい」「自分が今抱えている地域課題や活動課題と同じような事例を共有できて、とても参考になった」など、様々な収穫を得たことによる満足感が伝わってきた。
また最後の締めのあいさつは、大臣官房審議官(地域活性化担当)の佐藤啓太郎が務めた。

現役協力隊員
大分県日田市地域おこし協力隊 中村さん
「今年初めて参加しました。私の活動する中津江村は人口600人の小さな村なのですが、類似の事例や中山間地の事例を共有できて満足しています。着任6か月でまだ地元に自分の存在や活動が知られていないので、どういう方針で活動するか、3年の計画を立てて、村の将来像(観光開発)を地元に受け入れてもらうようにしていきたいですね。」

現役協力隊員
群馬県沼田市地域おこし協力隊 高橋さん
「初めての参加です。群馬県北部エリア5地域でブランドチームを立ち上げて広げる活動をブースで展示しました。来ていただいた方に企画を理解してもらえたり、応援グッズを買っていただいたり、とても嬉しく思っています。今は地元の伝統工芸である下駄づくりの修行中で、主に地元のおばあちゃん世代が買ってくれるのですが、今後はもっと全国に広げたいのでかわいい下駄を作ってネット販売していきたいですね。」

自治体職員
北海道余市郡仁木町 干場さん
「初めてのサミット参加でしたが、様々な地域の人がいて、うちの隊員と一緒に刺激を受けました。私は1年目でいろんな方の話を聞けてとてもためになりました。うちの町では隊員から逆提案してもらう形をとってもらっていますが、他の地域ではまた別の地域課題や解決・サポート方法があることを知れてよかったです。」

現役協力隊員
愛媛県西予市地域おこし協力隊 山口さん
「去年のサミットは普通に参加しただけですが、今年はブース出展をしたので、いろんな人がいろんな地域に興味を持っていることが分かりました。また協力隊の方も自分の地域だけでなく、他の地域ではどんな取組をしているか、すごくチェックしているのも感じましたし、協力隊になっていない方も、リアルな協力隊の活動をじっくり見ているなと思いました。もうすぐ任期終了ですが、今の地域で起業に向けて準備しています。」

協力隊員OG
島根県雲南市地域おこし協力隊OG 三瓶さん
「今回がサミット3回目の参加でした。今年はワークショップを担当していたのですが、明るい雰囲気の中で皆さん仲良くなるのがすごく早い! 今はサポートデスクの活動もしていますが会員数が増えており、できることとできないことがあって課題を感じています。サポートデスクの都道府県ネットワークづくりが進んでいて、チームとして対応できる仕組みができてきているのはいいことですね。」
今回は、昨年開催された地域おこし協力隊10周年の節目を迎えてさらに1年が経過し、今後さらなる活動拡大へ向けた、新たな一歩を踏み出すサミットとなった。
サミットへの参加を心待ちにしていた方も多く、それだけに普段知り合う機会の少ない「全国の仲間との出会い」を求める熱を、これまで以上に実感した。
最後に、今回参加されたすべての皆さんの今後のご活躍を心よりお祈りしたい。